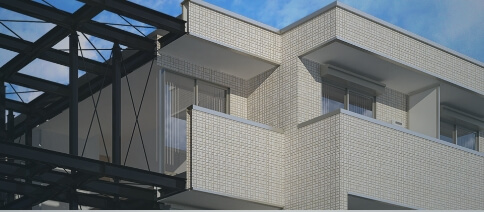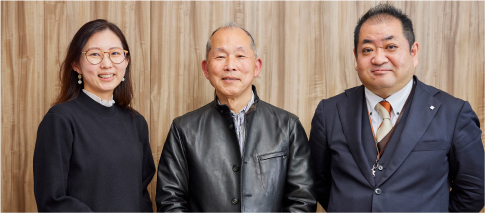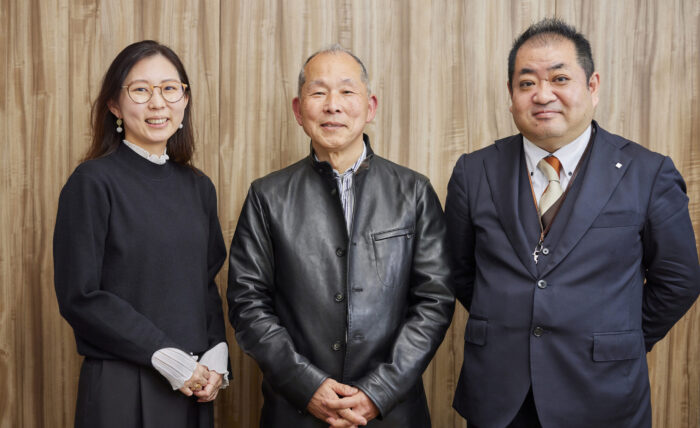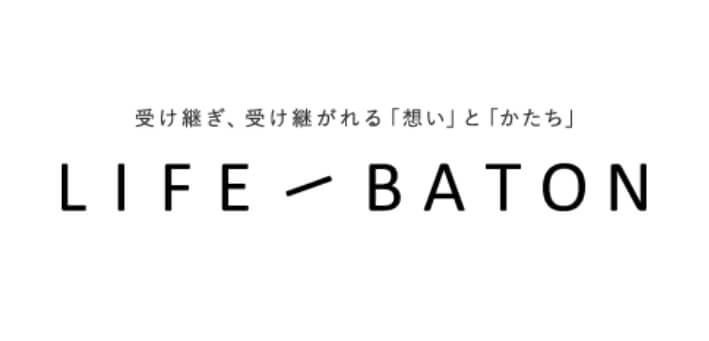Bringing the best smiles and emotions
to our guests.
About CEL

ゲスト(入居者)と
オーナーさまの人生を彩る
アパート専門メーカー
セレ コーポレーションは、人生設計の課題解決のためのコンサルティングから、自社工場での構造部材の製造、建築や空間設計、賃貸経営までアパート経営のすべてを手掛けるアパートメーカーです。事業エリアを東京圏(1都3県)に絞り、累計建築実績は約2,700棟(2023年2月現在)。
「アパート専門メーカー」として、これまで培ってきたノウハウを生かし、「ゲストに最高の笑顔と感動を」届け続けます。

Feature
空間・外観へのこだわりと
それを支える高い技術力。
 01
01空間の可能性を広げ、
多様な住み方を叶える
空間の可能性を追い求め、これまでにない暮らし方を実現。生き方にこだわる若者が、”行列をつくる”空間設計。
 02
02街ゆく人に、
住まう人に、いつも
いつまでも愛される建物を
街に、ゲストに、そしてオーナーさまに長く愛され、誇りになるデザインを目指したアパートブランド「My Style」シリーズ。
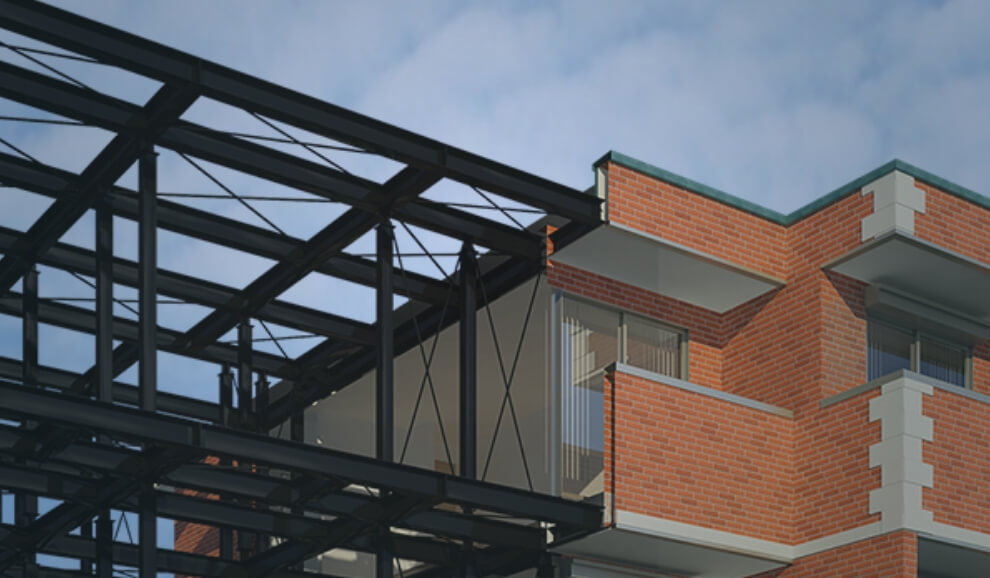 03
03ゲストの安全・
オーナーさまの安心を考えた
技術・設計
鉄骨造に特化し、主要構造部材を製造する自社工場を保有。国土交通大臣指定機関から型式認定・製造者認証を取得し、すべてのアパートが高い安全性と優れた耐久性をハイレベルで満たしています。
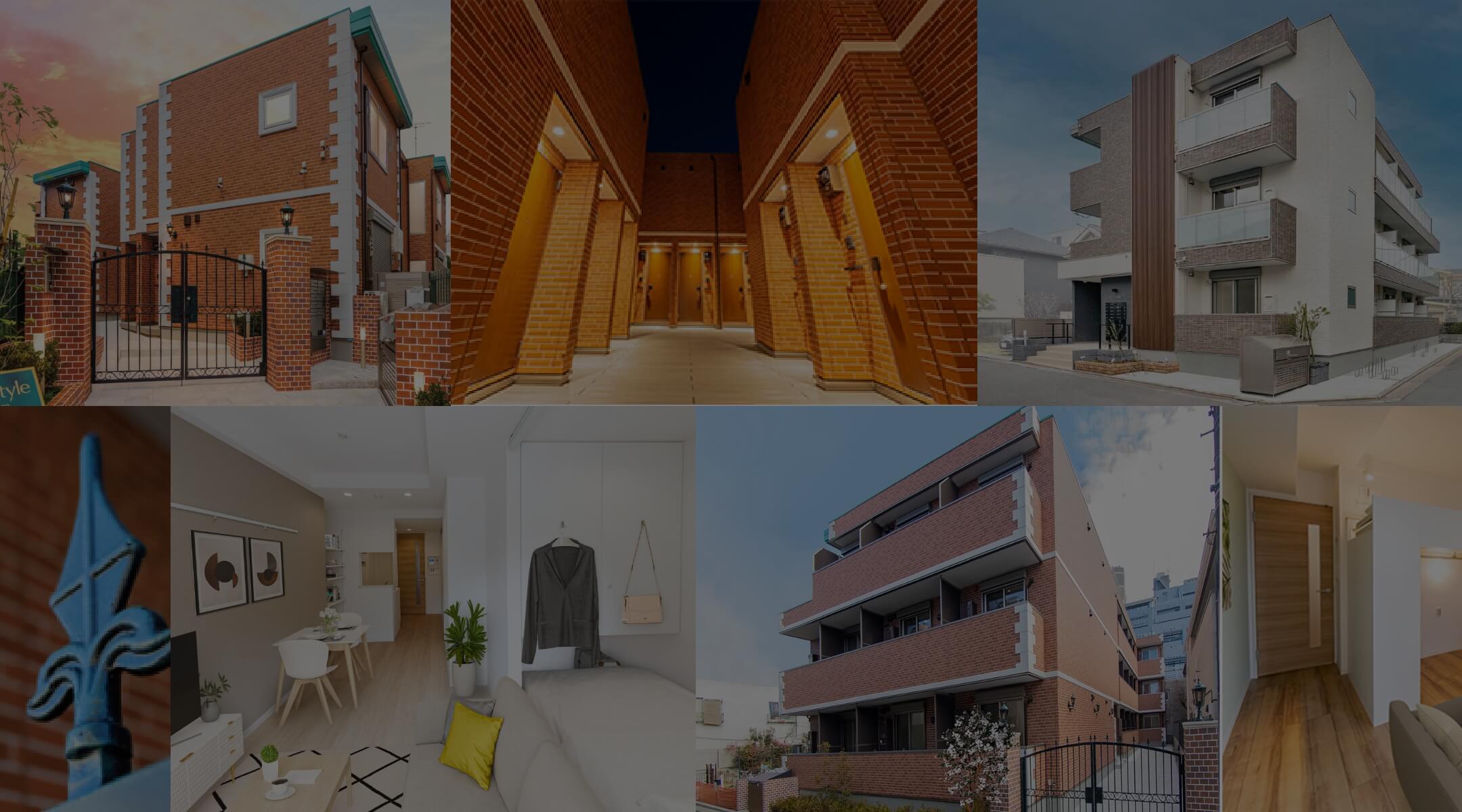

CaseStudy
実例集
アパートブランド「My Style」シリーズの建築実例と、
コンサルティング実例をご紹介いたします。
Support

安定したアパート経営を
持続していただくために
「アパート経営100年ドッグ」を掲げ、次の世代、さらにその次の世代へ
資産を承継していくためにアパート経営を長期的にサポートいたします。


Voice
オーナーさまの声
建築をお任せいただいた
オーナーさまの声をご紹介いたします。
ゲストの声
ご入居いただいた
ゲストの声をご紹介いたします。
News
お知らせ
| お知らせ | 「ゲストの声」を更新しました。 |
|---|---|
| お知らせ | 「オーナーさまの声」を更新しました。 |
| お知らせ | ホームページをリニューアルしました。 |
Reservation
ショールームの
来場予約はこちら
東京メトロ銀座線「京橋駅」直結のショールーム”セレ未来館”では、
赤煉瓦調の外観や空間設計、構造部材・壁の断面の模型などを常設展示しています。
Contact
まずはお気軽に
お問い合わせください。
アパート経営が初めての方もご安心ください。
お問い合わせ後は専任のコンサルタントがサポートさせていただきます。